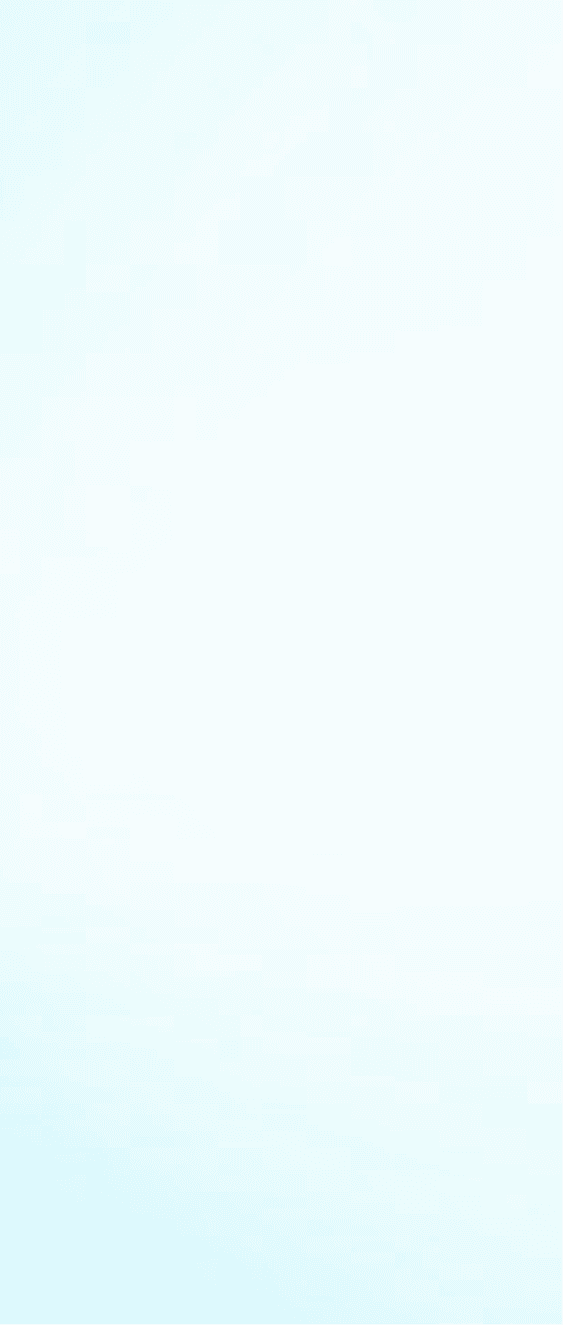
2025/05/15
コラム
「成熟できない日本」 ―日本人が忘れている二つのこと― ①
日本のあらゆるリーダーの方たちへの提案レポート
「成熟できない日本」 ―日本人が忘れている二つのこと― ①
今回は、4つのコラムに分けて少し骨太な問題提起をさせていただきたいと思います。
地盤沈下が続く日本にとって今取り組むべきことを書きました。
4つのコラムでお話したいことを手短に整理すると以下要約のようになります。
― 要約 ―
日本の経済的地盤沈下
日本経済は多くの指標で長期的な停滞傾向を示している。一人当たりGDPは1993年の世界2位から2023年には22位に低下し、労働生産性はOECD加盟38カ国中32位と低迷している。生産年齢人口も2056年までに26.4%減少する見通しである。また、年間6兆円を超えるIT貿易赤字(デジタル赤字)も大きな課題となっている。
二つの忘れられた根本課題
・真のリーダーの育成を怠ってきたこと
戦後のGHQ主導による『他律的』な改革は、日本社会に『他力本願』という甘えの構造を定着させた。教育システムも問題設定能力やリーダーシップを育てるよりも知識を求める姿勢を助長している。
・価値基盤の更新と継承を怠ってきたこと
「武士道」に代表される伝統的価値観の再評価と継承が行われず、共通の道徳や価値観を更新する努力も不足してきた。「多様な価値観」を標榜する一方で、根本となる共通基盤が希薄化している。
解決への処方箋
以下の対策を提案している:
・ リーダーシップ育成への国家的人材投資
・ 日本の骨格となる価値観の再構築と共有
・ 高齢者を「お荷物」ではなく「GDP生産者」と位置づける発想転換
・ 在留外国人の活用による生産人口の維持
・ 日本人の隠れたグローバル力の積極的活用
・ デジタル投資の拡大
・ 政治に対する信頼の回復
結論
日本の課題は「物価高」ではなく「所得の伸び悩み」が本質。しかしながら加工貿易に代わる明確な経済成長モデルを確立できていない。経済的地盤沈下と社会規範の空洞化を解決するには、リーダーシップの輩出と共有価値観の構築を基盤とした、新たな成長モデルの確立が不可欠である。
では、一つ目のコラムをお読みいただければ思います。
目次
1. はじめに
2. 株価復活とインバウンド好調の陰で地盤沈下し続ける日本
3. 加工貿易に続く経済モデルが見つからない
4. 社会的成熟度の地盤沈下が止まらない
1. はじめに
2024年は株価がバブル期のピークを越えるまでに回復し明るさを感じた。しかしこの喜ばしい事実が日本の構造的問題を覆い隠していることにわれわれは気づかねばならない。株価改善の陰で生産性の低迷や社会規範の空洞化など課題が累積しているからだ。
特にIT業界に身を置くものとして著者が憂いを感じるのは日本のIT貿易赤字、いわゆる「デジタル赤字」が巨額な点だ。2024年に年間6兆円を超えた。日本は世界で最大のデジタル赤字国だそうだ。
この赤字の原因はソフトウェアライセンスやスマホなどのIT関連機器やサービスを海外の巨大テック企業に大きく依存している一方でドイツのSAP社のように世界で活躍するITを生み出せていないからだ。
一方でインバウンド観光客数が大きく伸びて日本で消費した金額が2023年一年間で5.3兆円もありデジタル赤字をかなり相殺できているという考えがあるらしいが本当にそれで良いのだろうか。
このデジタル貿易不均衡は、日本の経済的な立ち位置に重大な脆弱性があることを示しているにもかかわらず、インバウンド観光客からの収入は日本の基幹産業の競争力喪失を覆い隠す危険な錯覚を生んでいる。
本報告書では、戦後80年を経ようとしている今、経済的地盤沈下と社会規範空洞化の背後に手つかずに存在し続けている二つの根本課題を明らかにしたうえでいくつかの処方箋を提案してみたい。
2. 株価復活とインバウンド好調の陰で地盤沈下し続ける日本
具体的な数字で日本経済の停滞状況を見てみたい。
まず「一人当たり国内総生産(Gross Domestic Product : GDP)」の国際比較をしてみよう。日本の一人当たり名目GDPの国際比較ランキングの推移は1993年に世界第2位まで躍進した。35,765.91ドルだった。円建てでは4,043,430円。
ところが日本のランキングは、円安の影響を受けドル建てで2023年に33,849ドルまで低下し韓国(35,563ドル)に抜かれ経済協力開発機構(Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD)加盟38カ国中22位まで降下したという。日本人の平均的な豊かさが大きく低下したことを実感させる結果である。(円建てでは、4,762,506円と1993年より増加している。)
次いで日本の「生産年齢人口」を見てみよう。国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口」では総人口は2056年に1億人を割り込む。このときの生産年齢人口の割合は52.8%と、1970年の60.9%から8.1ポイント低下する見通しだ。65歳以上の高齢者人口が増加し生産人口が大きく減るためだ。
比率でみると分母である総人口も減るため大きな減少に見えないかもしれない。しかし生産年齢人口の絶対数では1970年の7,157万人から2056年には5,265万人と1,892万人(26.4%)も減少する。これは東京都と福岡県の人口合計とほぼ同じだ。
次に「労働生産性」の国際比較に注目したい。公益財団法人である日本生産性本部が2024年12月に公表した「労働生産性の国際比較2024」を見ると以下の通りである。いずれも2023年の数字だ。
・ 日本の一人当たり労働生産性は、92,663ドル(877万円)。OECD加盟国中32位でこちらも主要先進7カ国中最も低い。
・ 製造業に限った場合日本の労働生産性は80,678ドル。OECDに加盟する主要34カ国中19位。イタリア(86,181ドル)やスペイン(77,973ドル)とほぼ同水準にあたる。
・ 日本の順位は2000年にOECD加盟国で一位だったものの2005年に9位、2010年に10位へと落ち込み、2015年以降をみると17~19位で低迷している。
「消費者物価推移」の国際比較をしてみよう。厚生労働省の社会保障審議会年金部会の「年金財政における経済前提」に関する専門委員会の資料を見ると以下のとおりである。
・ 1995年から2020年までの25年間の消費者物価指数の年間平均伸び率は、日本が0.2%であり物価の上昇は非常に緩やかだった。
・ 一方で海外各国のデータを見るとアメリカ2.5%、英国2.0%、フランス1.3%、ドイツ1.4%、カナダ1.8%、イタリア1.8%、韓国2.7%、オランダ1.9%と軒並み2.0%前後で推移している。
こうして改めて数字を整理すると労働人口が減少し続ける中で生産性が上がらず所得が伸びない状況が続いている。しかも海外との差は年々広がっている。
豊かさが低下しているにもかかわらず家計が大きく破綻しなかったのは消費者物価が大幅に上昇しなかったからだ。もちろん現在は輸入価格の上昇が消費者物価を急激に押し上げているが、それでも長期間で見れば伸びは日本の物価上昇は大変緩やかだ。
こうしてデータを整理してみると日本の経済問題の本質は「物価高」ではなく「所得の伸び悩み」だ。物価高に対する補助などは対症療法に過ぎず、未来を形作っていくためには、所得を大幅に伸ばす工夫と努力が求められている。
3. 加工貿易に続く経済モデルが見つからない
著者が小学生・中学生の1960年代1970年代日本は加工貿易の国だと教わった。加工貿易は原材料を輸入し製品に仕上げて輸出するモデルのことだ。
輸出額が輸入額を大きく上回ることで長い年月貿易黒字を達成してきた。このモデルは海外に比較して安い人件費と高い技術力で付加価値をつけることが前提だがもう一つの要因も忘れてはならないだろう。
対ドル360円の固定為替レートは1949年から1971年まで22年間続き、この大きく円安に振られた固定レートは日本の輸出産業に有利に働いた。そして戦後の復興と高度成長を成功させる原動力になった。
この頃エネルギーの自給率は高く、例えば1960年の日本のエネルギー自給率は58.1%。当時は高度成長の初期段階で多くのエネルギーを必要としたが日本は国産の石炭や水力で半分以上をまかなえた。高価な輸入エネルギーへの依存度は現在よりもかなり低く加工貿易の大きな障害とはならなかった。
1950年には朝鮮戦争が勃発し米軍向けの需要が急拡大する出来事も輸出に追い風となった。こうして加工貿易モデルに則って日本は国の経済成長を果たしたのだ。
このころベビーブーマーが誕生し旺盛な内需も高まりを見せた。国民誰もが生活レベルを向上させようと目標を定め一致団結して成長を遂げた。戦後復興という観点では大成功と言ってよい。
しかしながら戦後日本の高度成長を支えた「360円ドル固定相場」と「安価な労働力×高度技術」の組み合わせは、1985年プラザ合意による円高ショックで限界を露呈した。
著者が在籍していた日立製作所は2009年に製造業最大の赤字を計上して経営危機を経験したが、その後急速にグローバルな経営へ舵を切りデジタル企業への変貌を遂げて躍進している。
同社は経営幹部に外国人を迎え海外企業を買収し本格的なグローバル事業へ改革してきたことが効果を上げている。しかしこのような成功をおさめることができる企業は限定的だろう。製造業の大半が依然として伝統的ビジネスモデルからの脱却に苦戦しているというのが現実だと思う。
多くの企業にとってオリジナリティのある技術をもってグローバル事業を進められるようなモデルはいまだに見いだせていないといったら言い過ぎだろうか。
時代遅れとなった加工貿易パラダイムに代わる経済モデルは何かという根本的な問いはプラザ合意から40年を経ても大部分が未解決のままであり日本は明確な前進の道筋を見いだせていない。
先に日本の問題は所得の伸び悩みと書いたが、伸び悩みどころか低下している産業もある。日本のソフトウェアエンジニアの年間報酬額を海外と比較するとにわかには信じられないような低い数字だ。しかも年々低下し続けている。
人材派遣会社のヒューマンリソシア株式会社が定期的に発行しているレポートの最新版「2024年調査版データで見る世界のITエンジニアレポート(2025年2月)」によると米ドル建ての給与水準をみると日本は前年調査の26位から順位を落とし31位へ低下し$30,040にとどまる。日本円では450万円程度だ。
しかも、前年からの増減率は前回調査時より16.7%減少しており69カ国中59位。前年との比較では対米ドルレートは大きく変わっていないので、円建てでも低下しているということになる。これは非常に悩ましい。
同レポートでは「日本の給与水準が世界と比較して相対的に低下していることは、海外IT人材の日本への誘致において、障壁の一つとなる可能性があります。」と結論付けているが、海外から日本が魅力的に見えないのは、裏返せば日本から見て海外のほうが魅力的に見えるということだ。優秀な人材ほど海外に流出していってしまう事態を恐れる。
大手企業でのベースアップが大きく報じられている一方で、広く日本の産業を見ると所得の低下がみられる産業が存在するのだ。
4. 社会的成熟度の地盤沈下が止まらない
SNSではしばしば炎上が発生する。個人が批判の矛先に立たされて追い詰められてしまう。顔が見えず実名もわからないから何を言っても責任を問われないという構図が助長しているのだと思う。
世の中に「あこがれ」と呼べるような「人」が少なくなったことも影響を与えている気がする。「親ガチャ」というように若いうちから自分の人生にもう花はなく挽回するチャンスもないのだと未来をあきらめる若者が多くなってきている。頑張っても上に行けないのであれば、上に行こうとする者をいじめてやろうという気になってしまうのではないか。躓けば愉快だというわけだ。他人の不幸は蜜の味というけれど寂しい限りだ。
かつて「一億総中流」という言葉が流行した。大多数の国民が自分を中流階級だと考える意識を指し、高度経済成長期を経て1970年代に広まったものだ。このころ経済はどんどん上昇気流に乗っていたのでいつかは自分も上流になれるチャンスがあるという予感が持てた。
ところが今や格差は拡大し、やがて固定化されるようになってしまった。頑張った人やラッキーな人はそれなりに報われるがそうでなければ報われないという社会になってしまった。
格差を抱える一方で市民が共有するような道徳観・価値観もだいぶ怪しくなってきている。店員に対するカスハラも社会問題として取り上げられる。これは、条例や企業の行動指針などで対策するらしい。しかし、そうなる前に法律や条例といったルールでないと防止できないことが悲しい。法律以前に本来備わるべき個人の道徳観が低下したことが根本的な問題ではないのか。
2025年4月1日から施行された「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」は、全国初の業種を限定しないカスハラ防止条例だが対症療法に過ぎない。現状は個人の道徳判断が法規制依存に陥っていることを示唆している。
政治への不信感・無関心もひどい。日本の未来を創るための戦略と改革を訴える骨太なリーダーシップが見当たらない。議事場では足のひっぱりあいが続いている。どうでも良いような揚げ足取りに終始している。以下のように有権者の投票率と政治不信度の逆相関が示す統治システムの機能不全は深刻だ。
投票率は全体的に低下傾向にあり特に若年層で顕著だ。第一生命経済研究所や総務省、言論NPOなどのホームページを見ると
・ 2024年10月の衆議院選挙の投票率は53.85%で、戦後3番目に低い結果だった。
・ 2022年7月の第26回参議院選挙では、全年代平均が52.05%。
・ 若年層の投票率は特に低く参議院選挙では10代が35.42%、20代が33.99%、30代が44.80%と全年代平均を大きく下回っている。
それを裏付けるように政治不信の傾向が強まっており特に若い世代で顕著だ。
・ 政党や国会を信頼できないと考える国民が6割を超えている。
・ 政党に日本が直面する課題の解決を期待できないと考えている人は55.2%に上る。
・ 若年層(10~20歳代)の約7割が政治家を信頼できないと回答している。
・ 全年代において政府を「全く信頼しない」「あまり信頼しない」人が6割以上に達している。
この状況は政党間の建設的議論よりも政党間の力学に割く時間が優先される実態を反映している。明治期以降、長い苦闘の末に市民が得た民主主義であるけれど有権者は自ら選んだ政治家を信頼していないという由々しき事態だ。
日本の経済も社会も「日本の成長モデルはこれだ。それを支える倫理や価値観はこれだ。日本がこだわり世界を代表するものはこれだ。したがって日本の進むべき道はこれだ。」という明快な将来像を見いだせない現状はどうして起きてしまったのだろうか。どうすればよいのだろうか。
コラム2へ続く
2025年5月
ベストスキップ株式会社 シニアITコンサルタント 菅宮徳也
― 著者紹介 ―
大手電気メーカでIT関連の経験を積み2024年7月よりベストスキップ株式会社にてシニアITコンサルタントとして従事。

✓ 東南アジア向けメインフレーム営業・事業企画
✓ 金融機関向けITシステム活用研究・コンサルティング
✓ 金融機関向けシステムインテグレーション事業企画
✓ 米国ITシェアードサービス拠点設立・運営
✓ グループIT・セキュリティガバナンス
✓ グループ標準アプリ開発・運用
✓ 鉄道車両・信号システム事業部門(本社は欧州)の国内CIO
